日医工ジャーナル ダイジェスト
Vol.52 No.433 2025.7-9 ダイジェスト
 特集 特殊精密加工技術による医療機器開発の最前線
特集 特殊精密加工技術による医療機器開発の最前線
ものづくり姿勢の伝承とグローバルスタンダードへの対応

高山 隆志 氏
株式会社高山医療機械製作所 代表取締役社長
−−機械化による製造はいつ頃から考えていましたか。
【高山】僕は18歳で入社しましたが、機械化は入社時点から考えていました。入社してすぐにその準備に取り掛かり、34 歳で社長に就任、導入をスタートしました。
−−機械化の理由は何でしょうか。
【高山】手作業には「再現性」がない、つまり全く同じものを作ることができない。これが最大の理由です。当時、こうした考え方は誰にも相手にしてもらえませんでしたが、これからは機械化に進むしかないと確信していました。
私がこの世界に入ったのは1980 年代初頭ですが、当時から職人の成り手が減少していました。仕事の内容が手作業中心で、機械化されていなかったからです。機械化の最大のメリットは技術継承にあります。技術をデジタルで残すことができれば、従来の職人が行っているような“口伝”は不要となります。
−−22 歳の頃、バックパッカーとなってドイツの鋼製小物製造の機械化の視察に行かれたそうですね。
【高山】ドイツのトゥットリンゲン市を中心に3 ヵ月滞在しました。ドイツは医療機器の本場ですが、日本では情報が全くなかったからです。ドイツはかなり機械加工が進んでおり、鍛造製品の加工も機械で行っていました。しかし、加工方法は日本と異なり、使用している加工機械も全く違っていました。機械化するにしても、根本から自分で考えて作らなければならないと思いました。 従来の手作業による製造を行いながら、徐々に機械化への体制づくりを模索しました。通常の仕事をして夜10 時に帰宅し、パソコンを使って工作機械のプログラムの勉強を夜中まで行っていました。
−−当時、鋼製医療機器は外科医療の中心にありました。そうした時代に機械化、デジタル化へと舵を切った。
【高山】同業者からは変わり者と言われましたし、そんなことやって儲かるのか、と聞かれました。僕が考えていたのは、会社をマニュファクチャーにすること、機械化して自由に製品を作ることでした。自由設計でものが作れないと、今後は活動が難しくなるという考えが前提にあったからです。
 特集 特殊精密加工技術による医療機器開発の最前線
特集 特殊精密加工技術による医療機器開発の最前線
グローバル・ニッチで唯一無二の医療機器開発を目指す

河野 淳一 氏
株式会社河野製作所 代表取締役社長
−−御社は微細な製品の研究・開発・製造に携わってこられたとのことですが、どのようなきっかけで医療分野に進出されたのでしょうか。
【河野】弊社の創業は1949年ですが、当初は時計や計測器用の指針を製造していました。微細加工技術を活かし、医療機器の製造を開始いたしました。
−−当初、医師との関係はあったのでしょうか。
【河野】手の外科の医師からの依頼を受け、1974年にマイクロサージャリー用針付縫合糸を開発いたしました。その後も医師のニーズを受け、より細く、より小さい針付縫合糸の製造を行ってきました。当社が開発した直径0.03 mmの「世界最小の針」は、今まで不可能だった直径0.1 mmの血管縫合を可能にしました。
−−御社の“グローバルニッチトップ”というスローガンについて紹介してください。
【河野】世界の中でのニッチトップ(Niche Top)を目指すということです。グローバルな視点でニーズを見つけ出し、様々な分野やエリアにおいて100の市場創造を目指します。その第一弾がマイクロサージャリーです。
−−御社はどのような経営方針でしょうか。
【河野】常に挑戦する、ということです。加えて、希少疾患の患者さんが必要としているものを開発する、これが弊社の使命です。世界で唯一無二の製品である、大手企業が扱えない非常にニッチなマーケットだが切実なニーズがある、そうしたものは、すべて取り組み、医療技術の発展に貢献したいと考えています。
−−始めから世界市場を視野に入れ、開発に着手する日本の医療機器メーカーは珍しいです。海外市場についてはどのような考え方をお持ちですか。
【河野】例えば、中国です。弊社は販売拠点を置いていますが、製造拠点は置いていません。販売拠点にした理由は、中国の医師と組んで開発に取り組みたかったからです。活力があり、新しく伸びていく国には、必ず開発ニーズがあります。欧米は医療市場の成長が落ち着きつつありますが、中国やインド、ASEAN諸国では、今後、医療ニーズが生まれ医師数も増加します。中国は製造の下請けではなく、製品を売る市場と考えました。
 国内の医療機関における「コマンドセンター」の役割
国内の医療機関における「コマンドセンター」の役割
院内の医療情報を可視化し、医療の効率化を図る

松石 岳 氏
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 戦略事業本部 本部長
コンサルティング&ソリューション マネージング・ディレクター
−−日本の病院がコマンドセンターを採用するようになったきっかけは、何だったのでしょうか。
【松石】新型コロナウイルス感染症です。コロナ禍が起こった際、日本では医療従事者のリソース、病床確保が社会問題となりました。病床問題はなぜ起こるのか、どのように解決するべきか、それらを考えた時、コマンドセンターの存在が頭に浮かびました。2020年2月、新型コロナウイルス感染症が国内で蔓延し始め、この年の夏に我々はコマンドセンターのプロジェクトをスタートさせました。
コマンドセンターは新規事業です。新規事業を立ち上げる際、経営トップは既存の事業とシナジー効果が生まれるかどうかを考えます。ここが重要なポイントでした。我々は「コマンドセンターが同業他社との差別化を図る存在になり得るか」という視点でも話し合いました。最終の了承を得た時には、コロナ禍は拡大の一途をたどり、病床と医療従事者の不足が連日大きなニュースとなっていました。そのような中、我々のコマンドセンターは医療機関から注目され、少しずつ事業が進み始めました。日本で最初にコマンドセンターが導入されたのは2021年4月、滋賀県草津市の淡海医療センターでした。
コマンドセンター
病院内の多種多様なデータを包括的に解析、分析することで患者フローに関わるオペレーション全体を把握し、最適化するソリューションシステム。電子カルテや検査データなど院内の医療情報を統合的かつリアルタイムに可視化し、入退院業務の効率化と病床管理の負担軽減および質の向上を支援する。
コマンドセンターは、GEヘルスケアと米ジョンズ・ホプキンス大学医学部附属病院との共同開発により2016年に米国で開発された。2016年、2017年と継続的に運用したところ病床稼働率や救急受入、手術室の使用効率などが大きく改善した。
 【シリーズ】医療機器と私
【シリーズ】医療機器と私
手術のデバイスは私の身体の延長である 〜MT摂子開発の経緯〜
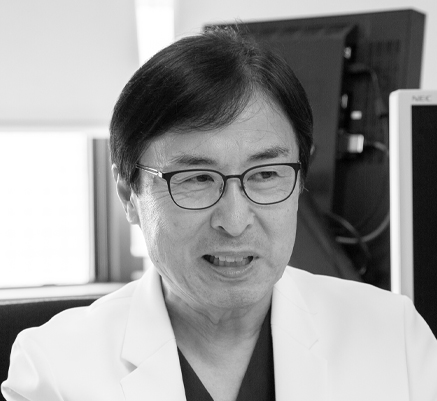
田邉 稔 氏
柏市立柏病院 院長/東京科学(旧 東京医科歯科)大学 名誉教授
MT摂子の開発のきっかけとなった米国留学
モノポーラ・ドベーキー型MT摂子の開発のきっかけとなったのは、1991年から1994年にかけての米国留学でした。ピッツバーグ大学の移植外科で肝臓移植を学ぶためのものでしたが、この手術は高難度で、消化器外科領域で最高峰の手術と言われていました。
留学最後の年にいろいろな施設を見学している中で、ネブラスカ州立大学のByers Shaw教授の手術に出会います。それは衝撃的なものでした。教授が使っていたのは通常のドベーキー型血管鑷子です。それを使用して把持だけでなく、助手がタッチして通電させることによる凝固+切離、いわゆる「ちぎり焼き」を行っていました。その手技は極めて迅速かつ正確であり、当時のピッツバーグ大学の肝移植レシピエント手術は10時間以上かかっていましたが、教授は半分の5時間で完了していました。
帰国した私は母校の慶應義塾大学病院に戻り、生体肝移植に取り組むことになります。私は、当時、国内で第一人者と言われた京都大学の田中紘一先生の手術を、何度か見学しに行きました。すると、なんと田中先生はByers Shaw教授とほとんど同じ手技を行っていたのです。当時の日米の人的交流を考えると、田中先生がネブラスカ州立大学に学びに行ったとは考えられません。おそらく、両先生が自然発生的に、この手技を編み出したのでしょう。偶然ですが、日本と米国で同じようなことが同時に行われていたのでした。
田中先生が多く手がけた小児生体肝移植の患者は胆道閉鎖症が多く、移植にいたるまでに何度も手術が行われていて、内臓のあちこちが高度に癒着して出血しやすい状態にありました。そんな状況の中で、着々と手術をすすめる正確無比な手技は、まさに芸術とも呼べるものでした。
このような名手の手技を手術機器によってさらに発展させようと思い、私がモノポーラ・ドベーキー型MT摂子の開発に本格的に取り組み始めたのは、2013年のことでした。
ジャーナルダイジェスト一覧
- No. 432 2025.4-6
- No. 431 2025.2-3
- No. 430 2024.10-2025.1
- No. 429 2024.7-9
- No. 428 2024.4-6
- No. 427 2024.2-3
- No. 426 2023.10-2024.1
- No. 425 2023.7-9
- No. 424 2023.4-6
- No. 423 2023.2-3
- No. 422 2022.10-2023.1
- No. 421 2022.7-9
- No. 420 2022.4-6
- No. 419 2022.2-3
- No. 418 2021.10-2022.1
- No. 417 2021.7-9
- No. 416 2021.4-6
- No. 415 2021.2-3
- No. 414 2020.10-2021.1
- No. 413 2020.7-9
- No. 412 2020.4-6
- No. 411 2020.2-3
- No. 410 2019.10-2020.1
- No. 409 2019.7-9
- No. 408 2019.4-6
- No. 407 2019.2-3
- No. 406 2018.10-2019.1
- No. 405 2018.7-9
- No. 404 2018.4-6
- No. 403 2018.2-3
- No. 402 2017.10-2018.1
- No. 401 2017.7-9
- No. 400 2017.5-6
- No. 399 2017.2-4
- No. 398 2016.9-2017.1
- No. 397 2016.5-8
- No. 396 2016.2-4
- No. 395 2015.10-2016.1
- No. 394 2015.7-9
- No. 393 2015.4-6
- No. 392 2015.2-3
- No. 391 2014.10-2015.1
- No. 390 2014.7-9
- No. 389 2014.5-6
- No. 388 2014.3-4
- No. 387 2013.10-2014.2
- No. 386 2013.7-9
- No. 385 2013.5-6
- No. 384 2013.2-4
- No. 383 2012.10-2013.1
- No. 382 2012.7-9
- No. 381 2012.4-6



