日医工ジャーナル ダイジェスト
Vol.50 No.427 2024.2-3 ダイジェスト
 日本における医療DXの現状と課題、そして展望
日本における医療DXの現状と課題、そして展望
〜病院同士が連携できる医療データの利活用が鍵〜

美代 賢吾 氏
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
医療情報基盤センター(CMII) センター長
−−いきなりですが、先生は日本の医療DXの遅れをどのようにお考えですか。
【美代】医療DXには2つの視点があります。1つは医療情報のデジタル化。大学病院を中心とした大規模医療施設ではかなり進んでいますが、中小規模の医療施設においてはそれほど進んでいない。こうした現状の二極化があります。
もう1つは日本の医療システム全体としてのデジタル化です。こうした広く大きな意味での医療DXは残念ながらほとんど進んでいないと言っていいでしょう。情報のデジタル化が進んでいる大規模医療施設が複数あるにもかかわらず、それを繋いで1つの大きな医療ビッグデータを作るなどの活用がされていない。日本では国内の病院を結んだ水平展開が行われていないと思います。
−−医療データの利活用ですね。日本ではなぜそれができないのでしょうか。
【美代】医療機関の最大のインセンティブが診療報酬だからだと思います。データをデジタル化しても診療報酬の加算とはなりません。
一方、米国の診療報酬制度は、病名によって診療にかかる金額が決められている診断群別包括支払い方式です。診療報酬内において最低限の医療行為で患者が治ったら、それだけ利益が大きくなる。つまり、他の病院で行った検査データがそのまま使用できれば、同じ検査を行う必要がないのでその分が利益になります。
しかし、日本の場合は外来の診療報酬は出来高制度なので、検査を行えば必ず収入となります。つまり、横に繋いで検査データを共有してしまうと、医療施設の収入が減ってしまう。医療DXを進めるためにはこうした医療制度を根本的に変えていく必要があります。この解決はなかなかの難問ですが、医療DXによる施設間の情報共有化が、医療効率の向上に繋がることを国にしっかりと認識していただきたいと思います。
 リクルート座談会
リクルート座談会
医療機器業界が優秀な人材を獲得するには?(前編)
和田 賢治 氏 一般社団法人 日本医療機器産業連合会 産業政策室 幹事/魅力発信部会 主査
株式会社 日立製作所 ヘルスケア事業本部 経営企画部 渉外担当 部長代理
相宮 直紀 氏 公益財団法人 医療機器センター 医機なび担当 主任
荒船 龍彦 氏 東京電機大学 理工学部 電子工学系 教授/博士(科学)
大西 信也 氏 ユフ精器 株式会社 総務部 人事課/経理課 マネージャー
佐久間 太郎 氏 第一医科 株式会社 管理支援本部 総務課
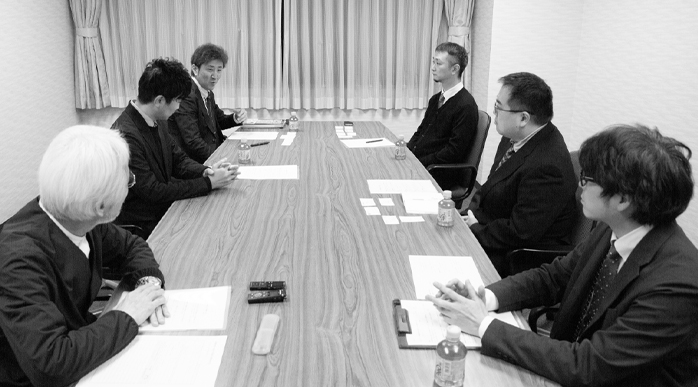
−−医療機器業界は人材確保に努力していますが、長年、厳しい現実に直面してきました。こうした状況は中小企業に限らず、大企業においても同様と聞いています。皆さんはその理由を何だとお考えですか。
【相宮】医療機器業界の人材獲得が難しい理由は様々あると思いますが、ここでは3つ挙げたいと思います。1つ目は業界が知られていないことです。薬機法上の広告規制等により、医療機器のテレビCMが流れることはほとんどありません。それ故に一般の方々がこの業界を知る機会は極めて少ないと感じています。
2つ目は一般の方々の場合、医療機器と聞いて具体的なものや働くイメージが浮かばないことがあると考えています。例えば、「医療」と「機器」という2つの言葉はどちらも非常に専門的な匂いを感じさせるので、特に文系の学生は自分とは関係のない業界だと思ってしまう方が多いみたいです。また、イメージが湧いたとしても命を支える仕事であるため、敷居が高いと捉えてしまうところがあることもわかっております。自分にできるのか、万一何かが起こった場合に責任を取らされるのか、そう考える学生も多いようです。
3つ目はこちらとしては意外だったのですが、医療機器業界のイメージをブラックに捉えていることです。テレビドラマやアニメの影響が大きいと考えていますが、医療機器業界は何か悪いことをしているのではないかと疑われているふしがあります。あるアニメでは登場人物が勤めている医療機器メーカーがブラック企業という設定になっていました。
 レポート/第4回医療用・介護用ロボット研究会(最終回)
レポート/第4回医療用・介護用ロボット研究会(最終回)
手術用ロボットに関する開発ガイドライン・国際規格等安全基準

鎮西 清行 氏
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 健康医工学研究部門 首席研究員
神戸大学 国際がん医療・研究センター 客員教授
「ロボット手術器具の洗浄プロセスに関する開発ガイドライン」について
ダヴィンチが病院に導入されるようになると、医療現場からは指示通りに洗浄しても、残留物が推奨許容値の数倍に達する、実際に内部を開けてみると血糊のようなものが残っているなどの報告が上がるようになりました。
その原因の1つは、ダヴィンチの手術器具が分解できない点にありました。つまり内部をブラッシングすることができない。通常の手術器具は、分解してブラシできちんと洗浄できることが前提です。ダヴィンチの手術器具は内部が複雑で、複数の部品が相対的に動作するリンク機構が導入されていました。医療現場はメーカーの指示通りに洗浄し、品質を担保するしか方法がありません。メーカーが適切な洗浄指示をすることは極めて重要です。
2つ目は洗浄工程の指示が複雑な点です。推奨しているのは用手洗浄のみで、指定の機械洗浄が極めて少ない。今後、予想されるのは、ロボット手術器具を製造するメーカーが増えることです。以前ならダヴィンチだけに対応すれば良かったが、異なるメーカーの製品が複数出てくることによって洗浄工程を変えなければならない。いろいろな製品が共存することによって現場が混乱する可能性があります。
そうした理由から洗浄プロセスに関する開発ガイダンスを作成しました。基本的には日本医療機器学会の「医療現場における滅菌保証のガイドライン2021」に沿って書かれたものです。しかし、このガイドラインには洗浄した際、どのようにテストするか記載されていません。今回はそういった点が加味されています。
 シリーズ 日本の医療機器業界で働く外国人社員に聞く
シリーズ 日本の医療機器業界で働く外国人社員に聞く
電子ペーパーから医療機器への転向
開発は変わらず前向きな姿勢で

Danilo Legaspi(レガスピ・ダニロ)さん
オリンパスメディカルシステムズ株式会社
デザインV&Vエンジニアリング2 V&V効率化推進
シニアプロダクトエンジニア
−−オリンパスと言えば何といっても内視鏡です。全世界の消化器内視鏡の7割のシェアを占める医療機器のリーディングカンパニーと見なされています。そのオリンパスで医療機器開発を担当して10年、開発の仕事はいかがですか。
【ダニロ】医療機器の開発は、品質要求が高いため作業工程も多く、期間も非常に長い。しかし、グローバル展開にはそれがネックになります。開発期間をさらに短くするには、効率的な計画を立てなければなりません。
−−開発期間が長いのは、日本の医療機器メーカー全てが抱える課題だと思います。
【ダニロ】上市にかかる期間が短縮できないと日本の医療機器メーカーのグローバル展開が難しくなると思います。また、製品のラインナップが多いこともグローバル展開には不利となりかねない。グローバル展開する企業の製品は、厳選する方向に向かっています。
また、同じオリンパスであるにも関わらず、国や地域によって開発の流れが異なります。先ほど言ったように日本の場合、海外に比べて開発に掛かる期間が長い。米国や欧州のオリンパスの社員はそれが不思議だと言っています。しかし、私が入社した10年前に比べたら、開発の期間はだいぶ短くなりました。開発を少しでも早く行うのは弊社だけの課題ではありません。とにかく、競合する海外企業に勝つためには努力する必要があります。
ジャーナルダイジェスト一覧
- No. 432 2025.4-6
- No. 431 2025.2-3
- No. 430 2024.10-2025.1
- No. 429 2024.7-9
- No. 428 2024.4-6
- No. 427 2024.2-3
- No. 426 2023.10-2024.1
- No. 425 2023.7-9
- No. 424 2023.4-6
- No. 423 2023.2-3
- No. 422 2022.10-2023.1
- No. 421 2022.7-9
- No. 420 2022.4-6
- No. 419 2022.2-3
- No. 418 2021.10-2022.1
- No. 417 2021.7-9
- No. 416 2021.4-6
- No. 415 2021.2-3
- No. 414 2020.10-2021.1
- No. 413 2020.7-9
- No. 412 2020.4-6
- No. 411 2020.2-3
- No. 410 2019.10-2020.1
- No. 409 2019.7-9
- No. 408 2019.4-6
- No. 407 2019.2-3
- No. 406 2018.10-2019.1
- No. 405 2018.7-9
- No. 404 2018.4-6
- No. 403 2018.2-3
- No. 402 2017.10-2018.1
- No. 401 2017.7-9
- No. 400 2017.5-6
- No. 399 2017.2-4
- No. 398 2016.9-2017.1
- No. 397 2016.5-8
- No. 396 2016.2-4
- No. 395 2015.10-2016.1
- No. 394 2015.7-9
- No. 393 2015.4-6
- No. 392 2015.2-3
- No. 391 2014.10-2015.1
- No. 390 2014.7-9
- No. 389 2014.5-6
- No. 388 2014.3-4
- No. 387 2013.10-2014.2
- No. 386 2013.7-9
- No. 385 2013.5-6
- No. 384 2013.2-4
- No. 383 2012.10-2013.1
- No. 382 2012.7-9
- No. 381 2012.4-6


