日医工ジャーナル ダイジェスト
Vol.51 No.431 2025.2-3 ダイジェスト
 医療ツーリズムの現状と国際医療コーディネーターの役割
医療ツーリズムの現状と国際医療コーディネーターの役割
山田 紀子 氏 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 国際医療事業部 部長
山本 修 氏 IMSグループ 株式会社アイセルネットワークス 国際事業部 部長
若林 恒平 氏 株式会社SMC 東京事務所 メディカルツーリズム部 チーフマネージャー
田中 耕太郎 氏 メディポリス国際陽子線治療センター 事業推進本部 医療連携推進部 部長

−−医療界ではここ数年医療ツーリズムが注目されるようになりました。日本では2011年に医療滞在ビザが創設された際にも話題になったと思います。日本における医療ツーリズムの流れを教えていただけますか。
【田中】タイでは2002年に国民皆保険制度ができました。そのころから民間の病院が個別に外国人患者の獲得を目指すようになり、2006年頃から急に外国人患者が増え、日本からも行政や医療関係者が視察で訪れるようになりました。
バンコク病院で働いていた私は日本で講演するようになりましたが、当時の日本の医療界は医療ツーリズムに対してネガティブでした。厚生労働省や日本医師会は医療ツーリズムに対して反対の立場を取っていましたし、セミナーを開催しても医療ツーリズムという言葉は使ってはいけないなどの制約がありました。その時期の日本は経済がそれほど悪くはなかったので、医療ツーリズムの動きは自然消滅となりました。
今回の医療ツーリズムの潮流は2度目であり、この流れは2016年頃から起こっています。コロナ禍によって一時中断されましたが、現在はそれも落ち着いて病院としてはこれから外国人患者の獲得に向けて本腰を入れるところでしょう。
【山田】医療ツーリズムという言葉が広まる頃に、経済産業省が医療の産業化の一つとして外国人に医療サービスを提供してもいいのではないかということを議論し始めました。当時医療ツーリズムは医療観光とも呼ばれて観光庁でも議論が始まったと記憶しています。2013年に政府・医療界・医学会などと連携することを目指して一般社団法人Medical Excellence JAPAN(MEJ)が設立されました。この頃から徐々に外国人に対し、医療提供しようという雰囲気が醸成されてきたと思います。
【若林】私が所属する株式会社SMCは、元々北海道を中心に活動している医療機器販売会社です。北海道では2006年頃から日本のTVドラマの影響で、中国からやって来る観光客が多くなりつつあり、次第に飛び込みで治療して欲しいという中国人の患者さんの声が挙がるようになりました。弊社は中国人相手の業務を手伝いましたが、その頃は事業になるとは思っていませんでした。
ところが、2010年に閣議決定された新成長分野の中で「国際医療交流(外国人患者の受入れ)」という言葉が登場します。弊社は外国人相手の医療施設紹介業務が事業として成り立つのではないかと考え、SMCの関連会社として株式会社メディカルツーリズムジャパンを設立しました。
 浜松医科大学が出資し、産学官連携を行う
浜松医科大学が出資し、産学官連携を行う
はままつ共創リエゾン奏 を設立
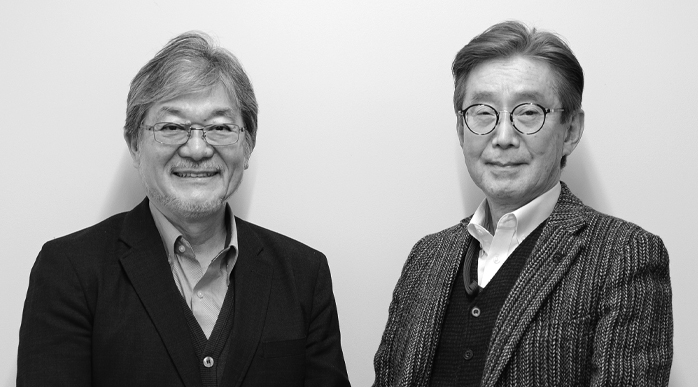
山本 清二 氏
株式会社はままつ共創リエゾン奏 代表取締役
脳神経外科 医師
鈴木 正人 氏
株式会社はままつ共創リエゾン奏 取締役
プロデュース部門長
はままつ共創リエゾン奏の設立の始まりは、2011年に科学技術振興機構の地域産官学共同拠点整備事業に採択された「はままつ医工連携拠点」にまでさかのぼります。この事業体を提案したのは、産業界からは浜松商工会議所と浜松地域イノベーション推進機構、大学からは浜松医科大学と静岡大学、光産業創成大学院大学、官は静岡県と浜松市が参加しました。光・電子技術とものづくり技術、医療・医学の融合を目指したもので、医療現場との情報交換会や人材育成セミナー、医工連携出会いのサロン、医工連携スタートアップ支援事業などさまざまな活動に取り組みました。2018年に完成した「浜松医科大学・医工連携拠点棟」を舞台に産学官が連携して医療と工学・工業の融合をさらに推進しました。
2011年から2023年の間に、医工連携の成果として製品化されたものは20件に及びます。代表的なものとしては「光学式内視鏡手術ナビゲータ」、「喉頭内視鏡システム(デジタル喉頭ストロボ)」、「手術器具保全・管理支援システム」、「赤外線眼振画像記録装置」、「次世代PET装置」、「立体外視鏡」などがあります。
浜松市はスズキ、本田技研工業、ヤマハ発動機、ヤマハ楽器、河合楽器製作所、浜松ホトニクスなどを生み出した創業者の街として知られています。多数のスタートアップ企業が集まり、創業から成長までのプロセスが次々と展開される好循環の環境が整っています。2023年のスタートアップの創業数は25社、市外からのスタートアップの進出が14社、年間の資金調達学は約53億円に上りました。アントレプレナーの街として面目躍如といった感があります。
 リクルート座談会 新卒採用編
リクルート座談会 新卒採用編
国内医療機器業界の新卒採用をどのように考えるか(後編)
堀野 賢一郎 氏 専修大学 キャリアセンター事務部 次長(大学職業指導研究会 事務局長)
成澤 崇禎 氏 拓殖大学 就職キャリアセンター 就職部 就職課長(全国私立大学就職指導研究会 事務局長)
瀧野瀬 浩晃 氏 サクラファインテックジャパン株式会社 人事・総務部 部長
兒玉 友 氏 アトムメディカル株式会社 HRコネクテッド部 人事総務課 課長代理
相宮 直紀 氏 公益財団法人 医療機器センター 医機なび担当 主任

−−本質的な課題について意見を伺いますが、医療機器・ヘルスケア業界に優秀な人材が集まるためには、どのような課題をクリアしなければならないとお考えですか。
【成澤】こうした課題は、大学と企業が連携して取り組まなければならないでしょう。そのためには両方の交流の場を深める必要があると思います。
【堀野】私も同意見です。医療機器業界に詳しい職員はそういませんから、企業から大学のキャリアセンターに来ていただいて、「こういう企業がある、こういう働き方ができる」など、業界について職員にレクチャーして欲しいですね。
学内の合同企業説明会を企画する際は、これまでに訪問してくださった企業を中心にお願いするようにしています。熱心な企業の話は学生に伝わるので、十分な周知が図れます。その企業に新卒が就職するようになれば、後輩が続くという流れになるでしょう。
【瀧野瀬】企業側としても大学と企業の連携は賛成です。企業側の視点だけでは考え方が偏ってしまうということがわかりました。お話を聞いていて、入社後の新人に会社の社会貢献について、具体的な内容を伝えられていなかったと感じます。企業としては「こうした社会貢献が実践されている」と入社後の新人が認識できる場をもっと設ける必要があることを理解しました。そういった意味でも大学との連携は必要だと思います。
【兒玉】まず、我々から一歩踏み出していくべきでしょう。そして、弊社一社ではなく業界全体がアピールしていく姿勢で取り組むべきだと考えさせられました。
 目標は微細手術用の手術支援ロボットの開発
目標は微細手術用の手術支援ロボットの開発

鈴木 与志成 氏
三洲電線株式会社 代表取締役社長
−−どのような理由で数ある医療機器業界団体の中から日医工を選んだのでしょうか。
【鈴木】シスメックス株式会社の浅野さんからロボット研究会についてお聞きしたことが、直接のきっかけとなりました。実は、日医工に入会する以前から浅野さんに手術支援ロボットの開発や普及について相談をしていたのです。浅野さんから、日医工で医療用・介護用ロボット研究会が発足されるという話を聞き、迷わず日医工に入会しました。
−−業界団体に参加することの利点をどのようにお考えですか。
【鈴木】私にとっての利点は計り知れません。なかでも最も重要だと感じたのは人とのつながりです。医療機器ビジネスを展開していくうえで、日医工の会員企業の皆さんとのおつきあいは非常に大切なものとなりました。例えば、日医工さんに入会して知り合ったのが、現在弊社でメディカルアドバイザーを務めている藤田氏です。また、元々弊社だけでは行政との対応は心許ないと考えていました。日医工という医療機器メーカーの業界団体に所属しているからこそ、厚生労働省や経済産業省との関係が上手くいっているのだと思います。
−−医療機器業界への参入はハードルが高いと言われていますが、実際どのように感じましたか。
【鈴木】やはり参入障壁の高さを感じました。医療機器開発の承認申請から保険適用にいたるまでの手続きは、非常に高度なうえに複雑です。弊社と同じケーブルメーカーでも参入したいと考えている企業がありますが、参入に成功した企業は3、4社でしょう。ましてや、弊社のように医師と直接コンタクトをとって製品を開発しようとする企業は皆無です。
そういう状況ですが、弊社は私の一途な気持ちで医療機器事業を進めています。本業をしっかりと行っていく一方で、新しい分野にもチャレンジしたいと思っています。
ジャーナルダイジェスト一覧
- No. 432 2025.4-6
- No. 431 2025.2-3
- No. 430 2024.10-2025.1
- No. 429 2024.7-9
- No. 428 2024.4-6
- No. 427 2024.2-3
- No. 426 2023.10-2024.1
- No. 425 2023.7-9
- No. 424 2023.4-6
- No. 423 2023.2-3
- No. 422 2022.10-2023.1
- No. 421 2022.7-9
- No. 420 2022.4-6
- No. 419 2022.2-3
- No. 418 2021.10-2022.1
- No. 417 2021.7-9
- No. 416 2021.4-6
- No. 415 2021.2-3
- No. 414 2020.10-2021.1
- No. 413 2020.7-9
- No. 412 2020.4-6
- No. 411 2020.2-3
- No. 410 2019.10-2020.1
- No. 409 2019.7-9
- No. 408 2019.4-6
- No. 407 2019.2-3
- No. 406 2018.10-2019.1
- No. 405 2018.7-9
- No. 404 2018.4-6
- No. 403 2018.2-3
- No. 402 2017.10-2018.1
- No. 401 2017.7-9
- No. 400 2017.5-6
- No. 399 2017.2-4
- No. 398 2016.9-2017.1
- No. 397 2016.5-8
- No. 396 2016.2-4
- No. 395 2015.10-2016.1
- No. 394 2015.7-9
- No. 393 2015.4-6
- No. 392 2015.2-3
- No. 391 2014.10-2015.1
- No. 390 2014.7-9
- No. 389 2014.5-6
- No. 388 2014.3-4
- No. 387 2013.10-2014.2
- No. 386 2013.7-9
- No. 385 2013.5-6
- No. 384 2013.2-4
- No. 383 2012.10-2013.1
- No. 382 2012.7-9
- No. 381 2012.4-6


